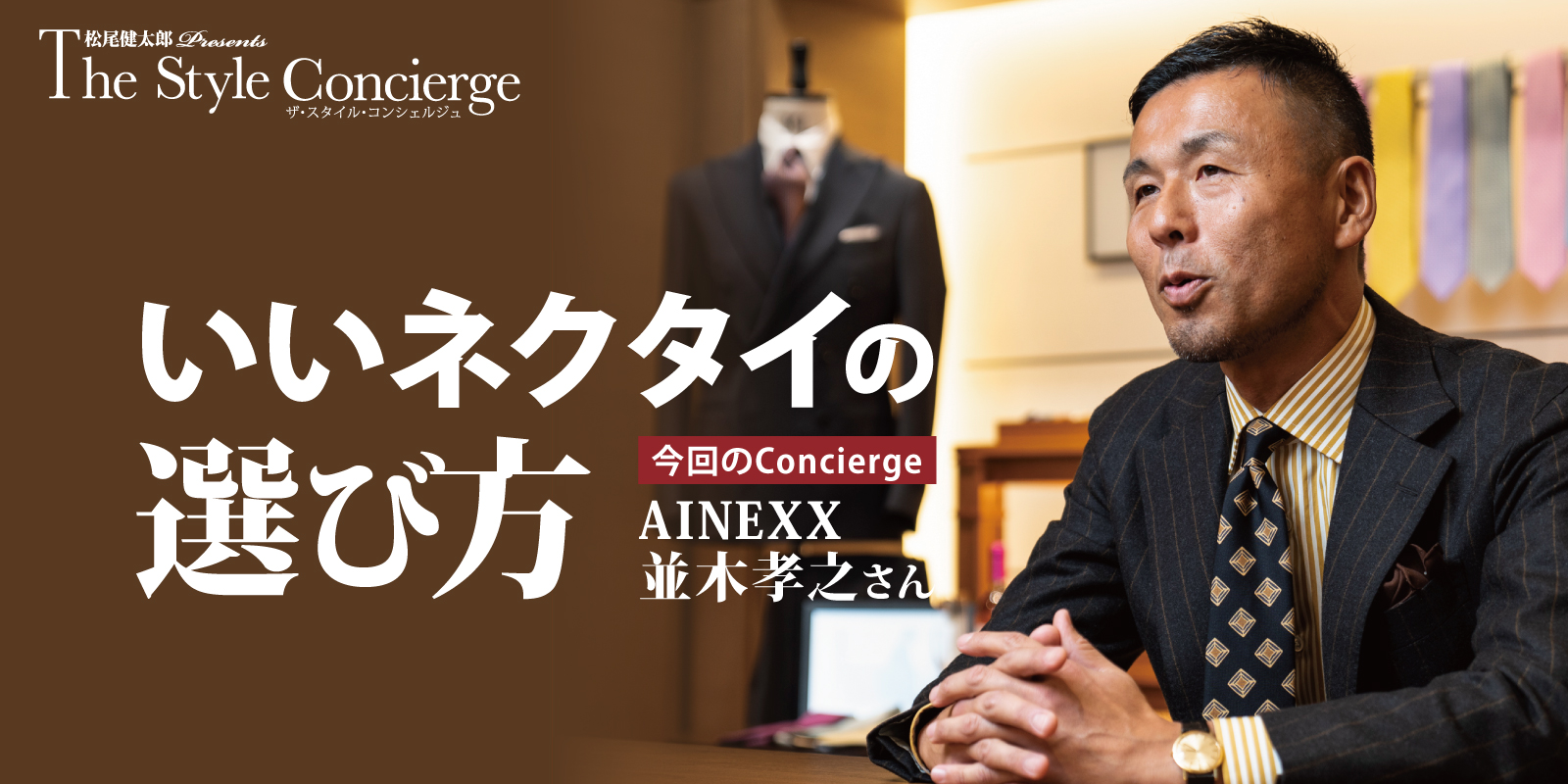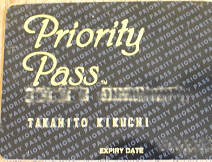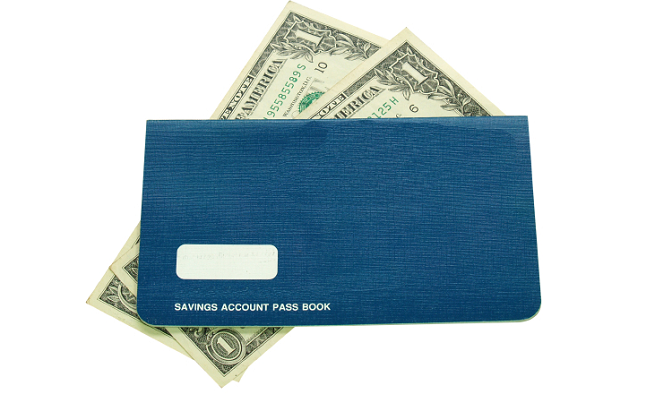
先日ちょっと気になるニュースがあった。戦後一貫してプラスが続いてきた日本の家計貯蓄率が初めてマイナスに転じたのである。今すぐに何かに影響するという話ではないが、今後、日本におけるマネーの動きや企業のビジネス・モデルが大きく変わる可能性がある。資産を保有している人にとっても、そうでない人にとっても、このニュースは頭の片隅にとどめておいた方がよいだろう。
貯蓄率が低下する最大の原因は高齢化
内閣府が2014年12月25日に発表した2013年度の国民経済計算確報によると、家計部門の貯蓄率がマイナス1.3%となり、戦後初めてマイナスとなった。
家計の貯蓄率は、可処分所得に対する貯蓄の割合を示している。これがマイナスになったということは、日本の家計全体として、手取り収入以上に消費を行っており、過去の貯蓄を取り崩して生活していることを意味している。
それぞれの家庭では、たくさん貯金をしている人もいるだろうし、常にカツカツで貯金に手を付けている人もいるだろう。だが、これらをすべて足し合わせた結果、日本人全体として、稼ぎよりも消費が多くなったということである。
貯蓄率が低下しているというと、消費が過剰であるとか、稼ぐ金額が少なくなったからというイメージを思い浮かべるかもしれない。実際、日本はここ20年、経済は伸び悩み、実質所得は減少している。日本全体として稼げなくなってきているのは事実である。
だがそれ以上に大きいのが高齢化の影響である。定年後も働く人は増えているが、現役時代と同じように稼げる人は少ない。それなりの資産がある運用益を得られる人以外は、貯蓄を取り崩して生活することになる。高齢者の割合は年々増加しているので、結果的に家計の貯蓄率も減少するという仕組みである。
マクロ経済的に見れば、家計の貯蓄は、国内の投資に充当される。投資する分よりも貯蓄が上回っていた場合には、最終的には経常黒字という形でそれが顕在化するか、政府が赤字の場合には、国債に充当される。日本政府が赤字を垂れ流しても平気だったのは、貯蓄率が高く、経常収支も黒字だったからである。
ところが貯蓄率が低下するということになるとそうはいかなくなる。貯蓄率の低下がどのような形で顕在化するのかを予想するのは難しいが、政府がこれ以上、借金を重ねることができなくなったり、経常収支が悪化してくる可能性は高い。貯蓄率が低い状態で多額の国債発行と経常黒字を両立することは難しいのだ。もっとも政府の赤字をすぐに減らすことは現実的に難しいので、貯蓄率の低下は経常赤字という形で顕在化すると考えた方が自然だろう。