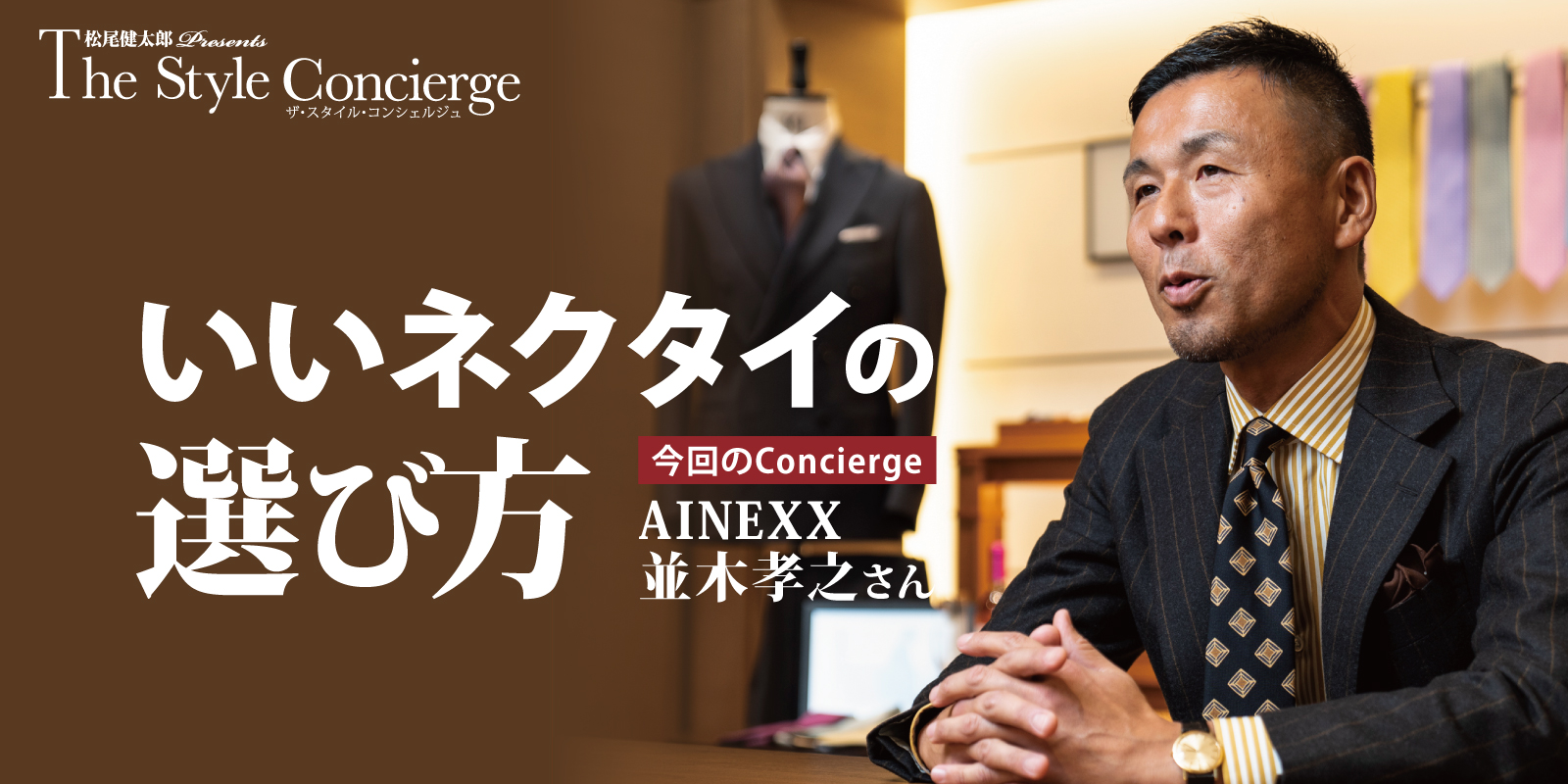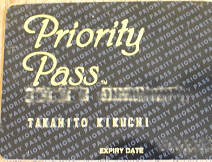変化を促すサインと考えるべき
経常赤字はマイナスのイメージで語られることが多いが、決してそうではない。経常収支が赤字であることを前提に適切な経済運営を行えば、順調に経済を成長させることができる(米国はずっと経常赤字だが、経済は絶好調である)。
経常収支が赤字ということは、付加価値の低いモノを輸入しているということであり、それは社会が成熟してきた証拠でもある。つまり、国内において、付加価値の高いサービス産業を育成する土壌が出来上がったということになる。一方、必要な資金の一部を海外からの投資に頼るということも意味している。
日本市場が魅力的であれば、海外からは良質な資金を集めることが可能であり、それをもとに、付加価値の高い産業を生み出すことができる。このスパイラルが構築できれば、経常赤字はまったく怖くない。新しいビジネスを考えている人にとってはむしろ大きなチャンスと考えるべきである。
だが、従来の日本型システムを変えず、新しい産業を国内に生み出すための努力をしないままでは、経常赤字になることの弊害がより目立つようになってくるだろう。貯蓄率の低下がどのような結果をもたらすのかは、日本が成熟型社会に転換できるのかどうかにかかっていることになる。
もっとも今回マイナスに転じたのは家計の貯蓄率であって、企業は依然としてたくさんの現預金を保有している。本来、企業はお金を貯め込む存在ではなく、積極的に投資をしてビジネスを進めていく存在である。その意味で、今の日本企業は完全に殻に閉じこもった状態にあるといってよい。
逆に考えれば、積極的にお金を使うはずの企業が過剰に現金を貯め込んでいることで、何とか日本政府の国債発行が続いてきたと解釈することもできる。だが日銀は量的緩和策という、背水の陣ともいえる金融政策に踏み込んでおり、企業がこれ以上、現金を保有することの合理性はなくなりつつある。
企業が貯蓄から投資に転換すれば、全体の貯蓄が減少してしまう可能性がある。だが、これがうまく作用すれば、最終的には個人の所得の増加につながり、高齢化が進んでも、家計の貯蓄をプラスに転換できることになる。結果として、量的緩和策も成功することになるはずだ。
家計の貯蓄率がマイナスになったということは、企業の現預金の貯め込みが限界に来ていることのサインと考えた方がよいだろう。日本企業が殻を打ち破るのか、このまま冬眠を続けるのか、決断すべき時が近づいているのかもしれない。