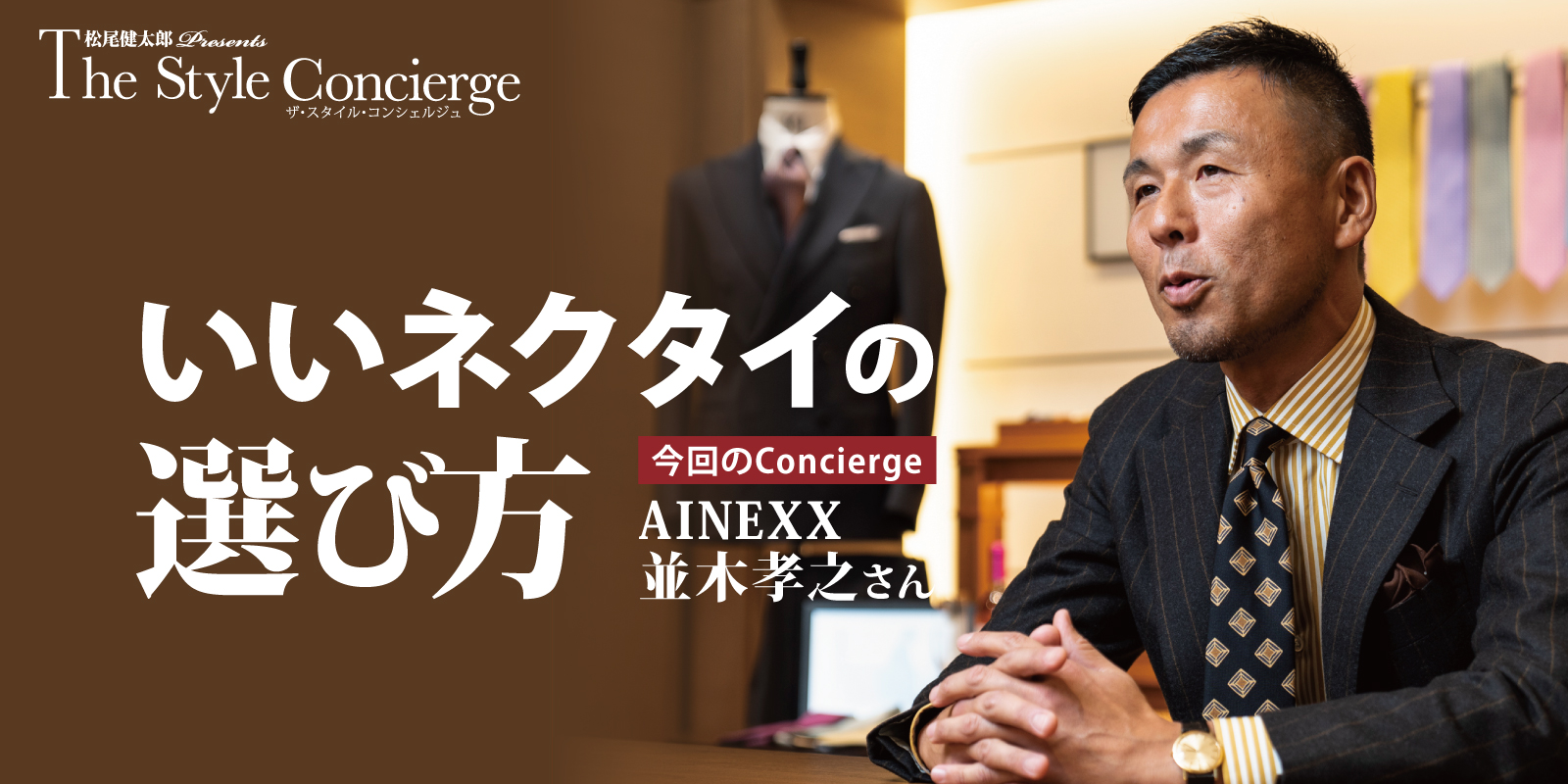国内外の遊覧船市場での活躍を想定
静かで快適な観光ニーズに応える
静粛性や操作性に優れ、メンテナンスの手間もほぼかからない。メリットの際立つ「HARMO」だが、どういったシーンでの利用が期待されているのだろうか。
「『HARMO』は低速に特化していて、最高速は時速9~10㎞。実際はそれ以下のスピードで航行することを想定し開発していて、多くの乗客を乗せて動く遊覧船などに向いています」
オランダ・アムステルダムの運河など、海外の観光地では遊覧船のニーズが高い。こういったシーンに「HARMO」の特徴がフィットする。
こういった点を想定し、昨年8月からは小樽運河で実証運航を行ってきた。同所のクルーズ船の観光需要な年々増加していて、2019年の総乗客数は延べ15万人にものぼるほど。ここでは全長9.8mで最大定員46名の船に「HARMO」を2機搭載、計500kgのバッテリーを積む。

「クルーズ船は1日中休む間もなく稼働しますが、運航中にバッテリーが切れることはなく、消費するのは半分くらい。営業が終わり夜の間に充電すれば、翌日に十分間に合いました。また、特徴の静粛性から『HARMO』を積んだ船だと船首から船尾まで声が届き、多くの乗客は『どうなっているの?』と不思議がるほどでした。狭いところでUターンしたり、他の船にぶつけないなど操船は大変なのですが、ジョイスティックによる操作で、スタッフの気遣いはかなり減ったと聞いています」
9月に始まった欧州の先行受注でも、遊覧船関連からの反響が多く。他には環境に配慮したい行政関係者からの問い合わせも目立ったそうだ。「我々としても当面は個人ではなく、法人からの需要を見込んでいます。加えて、船外機を積むボートビルダーとも協業するなど、徐々に市場を広げたい考えです」

ヤマハというと、日本ではボートやクルーザーを製造・販売するイメージが強いが、マリン事業を支えるのは欧米での船外機の販売だ。そう考えると、環境意識の高い海外の市場に向けて電動船外機をリリースするのは当然の流れであり、その波はそう遠くないうちに日本にもやってくるだろう。
「小型のボートからクルーザーまで、すべてを『HARMO』に置き換えるわけではありません。少なくとも、BEVやFCVを使い分けるなど、船のサイズや用途に合わせて、臨機応変に開発を進めていきたいと考えています」
自動車産業では、「Connected(コネクテッド)」「Autonomous(自動運転)」「Shared & Services(カーシェアリングとサービス)「Electric(電気自動車)」を推進する「CASE」が注目されていて、CASEを制する企業が今後の業界を制すると言われるほど。他方、ヤマハが目指すのは「マリン版CASE」の実現だという。
「CとAの領域ではIoT企業に出資をしたり、船外機用操船制御システムの『ヘルムマスターEX』を開発、Sの領域ではレンタルボートサービスの『シースタイル』を全国で展開しています。そして、Eの電動化に相当するのが『HARMO』です。ただし、『HARMO』は単なる電動推進器ではなく、ヘルムマスターの制御技術などを組み合わせて、より付加価値を追求する方針です」

こういった一連の取り組みを通じて、マリン版CASEやカーボンニュートラル社会の実現を目指す、ヤマハ。ボートをはじめとするマリンレジャー市場は、密を回避できるとしてコロナ禍でも堅調で、米国の業界団体が今年発表したレポートによると、過去13年間で2020年の市場がもっとも好調だったという。日本でも小型船舶免許の合格者が前年度比25.7%増の7万1975人にものぼるなど、盛り上がりを見せている。そうしたなか登場した「HARMO」が、これからどの様に受け入れられて行くのか注目したい。
*この記事は2021年12月に掲載されたものです
取材協力:ヤマハ発動機株式会社
TEXT:大正谷 成晴